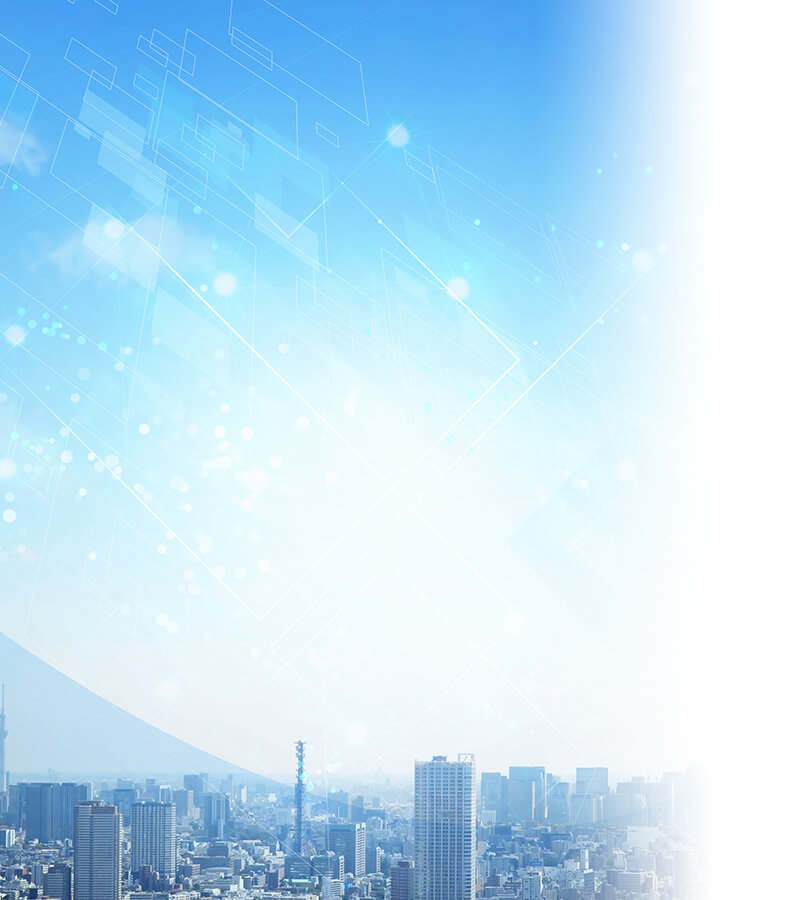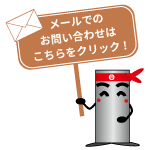Explanation of terms on the site
サイト内用語の解説

用語 あ行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| あ行 | e-pile next (イ-パイルネクスト) |
e-pile nextとは、建築・土木構造物等を支えるために、地中に埋め込む棒状の杭の先端に拡翼が設けてある鋼管杭基礎(国土交通大臣認定工法) 〈杭基礎、地盤改良、支柱、その他、地滑り抑止杭としても利用できる。〉 |
| x-pile next (エックスパイルネクスト) |
x-pileとは、小規模建築物等を支えるために、棒状の杭に拡翼が設けてある鋼管杭(建築技術性能証明工法) 〈主に小規模建築物等の地盤改良杭として用いられる。〉 |
|
| エヌ値(N値) | N値(えぬち)とは、標準貫入試験(JIS A 1219)によって求められる地盤の強度等を求める試験結果(数値)である。標準貫入試験値とも言う。 | |
| エコマーク認定 | エコマーク認定とは、様々な商品(製品及びサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。 | |
| エル型擁壁(L型擁壁) | 擁壁とは切土や盛土の際に、土圧による土の崩壊を防ぐために設ける壁のことです。L型とは、英字の「L」を基本にした形状〈高さ(m)≠基礎(m)〉で一般的擁壁モデルです。 |
用語 か行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| か行 | 回転圧入方式 | 回転圧入方式とは、杭を貫入させる際、杭打機械の反力(押圧力)と減速機(モ-タ-)による回転力とで貫入させる方式。一般的に直接貫入するため排出土がなく低騒音、低振動で行えるため周囲近隣への影響と環境負荷の少ない工法と位置づけられている。 |
| 瑕疵担保責任 | 瑕疵担保責任とは、引き渡しを受けた目的物の品質・内容が契約内容に適合しない場合に注文者に対して負う責任「契約不適合責任」と同義である。 | |
| 瑕疵担保保証 | 瑕疵担保保証とは、請負者が注文者に対し、瑕疵・欠陥が発生した場合の損失を予め保証することを約束すること。 | |
| 狭小地施工 | 狭小地施工とは、狭小な土地に計画される工事施工である。明確な定義はないが、一般に約15坪(50m2)以下の土地に建てられる住宅が狭小住宅と呼ばれ、普通自動車等の進入も困難な場合が多い。 | |
| 杭基礎 | 杭基礎とは、主に軟弱な地盤における構造物の建設において、浅い基礎では構造物を支えることができない地盤の場合に、固く安定した地盤まで深く棒状の杭を打ち込み、構造物を支える基礎をいう。 | |
| 杭打機 | 杭打ち機とは、建設機械の一つで建設工事や土木工事の際に、杭を必要な地盤中に貫入若しくは打ち込む機械である。 | |
| 鋼管杭 | 鋼管杭は、杭基礎の一つで、既成の鋼管を使用した基礎工法です。主な特徴は鋼管の優位性となる圧縮・引張・水平方向への高い強度を有する他、支持地盤の起伏による杭長を自由に調整でき、リサイクル性、排出土がでないことから環境配慮へも優れた基礎工法である。 | |
| 国土交通省大臣認定工法 | 国土交通省大臣認定工法とは、建築基準法の改正に伴い、国土交通大臣により指定された指定性能評価機関において評価され、国土交通大臣により認定を受けた工法いう。 | |
| 回転圧入方式 | 回転圧入方式とは、杭を貫入させる際、杭打機械の反力(押圧力)と減速機(モ-タ-)による回転力とで貫入させる方式。一般的に直接貫入するため排出土がなく低騒音、低振動で行えるため環境負荷の少ない工法と位置づけられている。 | |
| 環境負荷 | 環境負荷とは、環境に与える悪影響を指し、建設工事も決して例外ではなく、ここでは、人的要因で発生する産業廃棄物、土壌・大気・水質汚染等、振動・騒音などとする。 |
用語 さ行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| さ行 | 砂礫 | 砂礫とは、粒の直径が2mm以上の砕屑物。岩石が風化・浸食・運搬され生じた砕屑物(砕屑性堆積物)、または、岩石が人工的に破砕された砕屑物、及び、珊瑚・貝殻などの破砕物。主に河川の下流、河口、海岸、海底など、様々な堆積環境下で観察される。 |
| 地盤改良 | 地盤改良とは、地盤上に構築する構造物の安定性を確保するために、その地盤にセメント系固化剤や鋼管杭等を使用し人工的に改良を施すこと。 | |
| 地盤調査 | 地盤調査とは、一般的に建物を構築する際に、その地盤の強さや性質を現地、周辺を考慮し確認する試験。〈計画規模や条件により異なるが、その多くは標準貫入試験やスウェーデン式サウンディング試験により行われる。〉 | |
| 地盤保証 | 地盤保証とは、ある一定の地盤調査・解析・設計/地盤補強工事の技術を持った指定会社が、施した構造物に対し、一定の期間、金額を保証するものです。(一般的には直接施工を行った会社ではなく信頼できる第三者期間の保証が安心と考えます。) | |
| 支持力 | 支持力とは、建築物や構造物等の荷重を、地盤や基礎、杭基礎等で支えようとする力。 | |
| 深層混合処理工法 | 地盤の軟弱な層が地表から2m~8m程度の場合に有効な地盤改良工法です。軟弱な地盤とスラリー状にしたセメントミルクとを専用の施工機械で混合・攪拌を行い、円柱状の改良体を良好な地盤まで築造し建物の安定を図る工法です。 | |
| スウェーデン式サウンディング試験 | スウェーデン式サウンディング試験は、北欧のスウェーデン国有鉄道が1917年頃に不良路盤の実態調査として採用し、その後スカンジナビア諸国で広く普及した調査を、1954年頃建設省が堤防の地盤調査として導入したのが始まりです。1976年にはJIS規格に制定され、現在では戸建住宅など小規模建築物を建設する際の地盤調査のほとんどが本試験によって実施されております。 | |
| セメント系地盤改良 | セメント系地盤改良とは、セメント及びセメント系固化材を現地盤もしくは、プラント工場において土と混合・攪拌し、一定以上の地盤強度を人工的に構築する方法。 | |
| セメントミルク | セメントミルクとは、主に水とセメントを練り混ぜたもので、地盤改良材や基礎地盤の注入剤として多く用いられ、 水と共に各種混和材を加えることもある。 | |
| 浅層混合処理工法(表層地盤改良) | 地盤の浅い層(地表から2m程度)が軟弱な場合に有効な地盤改良工法です。軟弱な地盤とセメント系固化剤をバックホー等で、均一に混合・攪拌、締め固めを行い、地盤強度の高い安定した人工地盤を築造いたします。 | |
| 自立式擁壁 | 自立式擁壁(フ-チングレス擁壁)とは背面土圧と鉛直荷重を支えるための自立した壁(土留壁)。特徴としては、基礎ベースを必要としない杭基礎一体化構造で、掘削時における土の問題(移動・処理・軟弱化など)や、周囲への影響コストを最小限に抑えることができる。用途は傾斜地や高低差が伴う場所で多く利用され一般的にはコンクリ-ト構造のものが多い。(当社ではオリジナル工法のYOSAKUを意味する) |
用語 た行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| た行 | 低空頭杭打機械 | 低空頭杭打機械とは、上空制限に対応した杭打機で、機械全高が低いため安定性に優れ、駅や、高架下、工場等の室内施工などの高さに制限がある場所で使用される。 |
| 土壌汚染 | 土壌汚染とは、土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質が、自然環境や人の健康・生活へ影響がある程度に含まれている状態をいう。 | |
| 地質調査 | 地質調査とは、地層や岩体の分布およびそれらの相互関係や地質構造などを知るために行う調査。調査結果は地質図、地質断面図、地質柱状図などで示される。土木建設のための基礎地盤調査、防災調査、環境アセスメント調査などがある。 | |
| 土質 | 土質とは、土壌の物理的、力学的性質であり地盤の構成と状態の基本的性質。 |
用語 な行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| な行 | 軟弱地盤 | 軟弱地盤とは、腐食性物質や泥、多量の水を含み、圧縮性・地盤変形の多い軟らかい粘性土、腐植土、若しくは砂質土をいう。 |
| 粘性土 | 粘性土とは、砂と違って水を加えるとドロドロになり,乾かすとカチカチに固まる性質をもっております。粒子の大きさは、粘土(5ミクロン以下),シルト(5~75ミクロン)で粘土及びシルトの一部は粘り気があるため,これらを“粘性土”と呼びます。粘土鉱物には,岩石を構成する鉱物の一部や火山灰が熱や化学作用などによって変質したり,いったん水に溶けて再結晶したりしたものが15種類もあると言われています。 |
用語 は行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| は行 | 標準貫入試験 | 標準貫入試験とは、土の相対的な硬軟、締まり具合などを表わすN値をもとめるとともに、土の試料を採取し、地層構成を判断するための試験です。試験方法は、質量63.5kg±0.5kgのドライブハンマー(通称、モンケン)を76cm±1cmの高さから自由落下させてボーリングロッド頭部に取り付けたノッキングブロックを打撃し、ボーリングロッドの先端に取り付けられた標準貫入試験用サンプラー[1]を規定貫入量である30cm打ち込むのに要する打撃回数(=N値)を求めます。 |
| 不同沈下(不等沈下) | 不同沈下とは、基礎地盤の沈下に伴い、構造物の各部で不均一な沈下を生じる現象。不等沈下ともいう。一般に沈下が全体的に一様であれば構造物に破壊や変状を生じることは少ないが、不同沈下すると傾斜したり変形して亀裂(きれつ)を生じやすい。軟弱地盤上に構造物をつくる場合には、基礎地盤の圧密沈下に伴う不同沈下を十分考慮しておく必要がある。 | |
| フーチングレス擁壁 | フ-チングレス擁壁(自立式擁壁)とは、背面土圧と鉛直荷重を支えるための自立した壁(土留壁)。特徴としては、基礎ベースを必要としない杭基礎一体化構造で、掘削時における土の問題(移動・処理・軟弱化など)や、周囲への影響コストを最小限に抑えることができる。用途は傾斜地や高低差が伴う場所で多く利用され一般的にはコンクリ-ト構造のものが多い。(当社ではオリジナル工法のYOSAKUを意味する) | |
| 平板載荷試験 | 平板載荷試験とは、原地盤に直径30cmの載荷板を設置して段階的に荷重を載荷し、そのときの載荷荷重と地盤の沈下量から地盤の支持特性や変形特性などを確認する試験です。 |
用語 や行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| や行 | YOSAKU工法(フ-チングレス擁壁) | YOSAKU工法(フ-チングレス擁壁)とは、崖や傾斜地等、高低差が伴う場所で土砂の崩壊を防ぎ安定した土地成形を構築するための土留め壁として利用される、基礎ベ-スを不要とした杭基礎一体化構造のコンクリ-ト擁壁。 |
| 擁壁 | 擁壁(土留め壁)とは、土木工事で、土を切り取った崖や盛り土を保持するための壁状の築造物。かこい壁。 |
用語 ら行
| 50音 | 用途 | 解説 |
|---|---|---|
| ら行 | ラフタ-クレーン | ラフタークレーンはラフテレーンクレーンとも呼ばれており、ホイール式クレーンに属している。1つのエンジンを駆動源として走行、旋回、吊り上げなど全ての動作を行うことができ四輪駆動、四輪操舵システムを装備しているため、悪路での走行・作業に対応でき幅広い分野で活躍している。 |
| ラムサウンディング試験 | ラムサウンディング試験とは、動的コーン貫入試験に分類され、確実な支持層の確認を省力化で行えることのできる試験機械(オートマチックラムサウンディング機械)です。従来スウェーデン式サウンディング試験では、困難だった「N値30を超える地層」や「深度20mを超える測定」でも余裕を持った測定が可能で戸建て、中低層のRC造や鉄骨造、土木構造物に至るまで幅広い分野で活躍、期待をもたらす地盤試験機械です。 | |
| リーダー | リ-ダ-とは、通常の杭打ち作業では、減速機(モ-タ-)による回転力と機械自重の反力との合力により打設を行う。その際、減速機(モ-タ-)や、杭のガイドをしているのが、リ-ダ-となり一般的には杭打機械全面に垂直方向に取り付けてある鉄骨柱。 | |
| ロードセル式試験機 | ロードセル(荷重変換器)式試験機は、ひずみゲージを使用し、引張・圧縮・ねじり等の力を電気信号に変換する物で、測定目的により各種測定器(デジタル指示計、トランスミッタ、ひずみ測定器)に接続し、表示・出力(アナログ/デジタル)・記録・制御・監視(モニタリング)などを行います。 | |
| ローム層 | ロームとは、土壌区分の一つ。粘性質の高い土壌であり、シルトおよび粘土の含有割合が25~40%程度のものを指す。ロームで構成された地層をローム層という。この関東ロームは火山噴出物が粘土化したものといわれている。 | |
| 六価クロム問題 | 六価クロムとは、クロムの化合物のうち、酸化数が +6 の Cr(VI) を含むものの総称で、セメント及びセメント系固化材を使用し、地盤改良を実施すると、六価クロムが土壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあるため、地盤改良を計画する際には、あらかじめ現地盤の土を採取し、六価クロム溶出試験を実施した上で、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認し、施工を行うことが望ましいとされている。 |